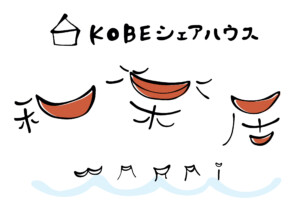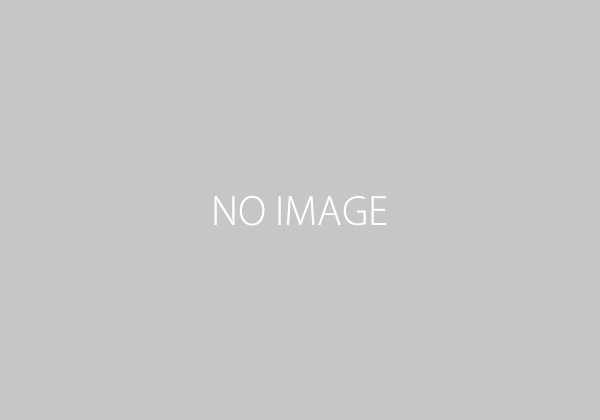聴き合う話し合いを通した対話会•心の探究会 1/23, 2/20(金)
こんにちは。 神戸シェアハウス和楽居(わらい)のいのじです。 2018年から、月に一度、聴き合う話し合いを通した対話の会『心の探究会』を開催しています。 人と輪になって、互いの気持ちを聴き合う中で、相手の本心や自分の本心が沸き上がってくる対話の時間です。 次は、1月23日, 2月20日(金) 12:30-16:00 聴き合う話し合いを通した対話会・心の探究会 (10:30 – 11:15 なんでもしゃべろう。交流タイム。 11:15-12:30 ご飯タイムやってます。 好きな時間にお越しください♪) です。 テーマは、その都度、その日の話題の中から湧き上がってきたものから決めています。 過去のテーマ一覧はこちら。 どんなテーマでやってるの? 近々塩屋heso.(ヘソ) さんでも再開予定! (神戸市垂水区塩屋町4-10-1) heso. facebook heso. instagram 心の探究会 / 聴き合う話し合いを通した対話の会とは? “聴き合う話し合い” という対話をベースにした、学び合い・気付き合いの場です。 輪になって、自分と対話し、みんなに聴いてもらいます。 そして、より深く自分の本心を知ったり、 人の事例を通して、人を知り、また自分を知るきっかけになったり。 「対話」のもたらす効能や意義 こちらでは、2つの論文や研究結果から、対話の効能や意義について考えてみたいと思います。 【対話の目的】 具体的な「課題」を解決し、組織を変革することにあります。 その達成のために、まずは「私たちは互いにわかりあえていない」という現実を前提とし、対話を通じて「関係性」を再構築することが重要です。 【対話による効能と意義】 表面的な問題ではなく、「何が本当の問題なのか」を再定義できます。 技術や権限だけでは解決できない、人と人との関係性に根差した「適応課題」を解きほぐします。 「この場では何を言っても大丈夫」という心理的安全性が確保され、率直な発言ができる関係が築かれます。 対話のプロセスを通じて、組織の課題が「自分ごと」となり、主体的な行動変容が促されます。 メンバー一人ひとりの個性や「こだわり」が発揮され、チームのポテンシャルが向上します。 【なぜ今「対話」が重要なのか】 社会の複雑化と不確実性 現代は、予測が難しく、単純な答えのない問題(正解のない問い)に満ちています。このような状況では、多様な視点を持ち寄って協力して考える対話が不可欠です。 従来のコミュニケーションの限界 どちらが正しいかを決める「議論」や、多数決で物事を進めるだけの「会議」では、問題の本質を見失ったり、新たな可能性を検討できなかったりします。 多様性を活かす必要性 グローバル化や価値観の多様化により、異なる背景を持つ人々との協働が必須です。個々の違いを「壁」ではなく「強み」として活かすために、対話が求められます。 参考文献1 組織において「対話」されるということの意義 論文著者 増田智香さん 所属:立命館大学立命館グローバル・イノベーション研究機構 【対話は「関係性の質」を高め、個人の幸福と組織の成長を両立させる鍵】 対話とは単なる情報交換ではなく、「相互理解を深め、関係性の質を高めるコミュニケーション」です。 「関係性の質」こそが、個人の幸福(Well-being)や成長と、組織の生産性や創造性を同時に高めるための土台となる。 個人の幸福感と成長 納得感(腹落ち)の醸成: 自分の考えを伝え、相手の考えを深く聞くことで、物事に対する納得感が高まります。 Well-beingの向上: 上司との対話が多い人ほど、幸福度や満足度が高い傾向にあります。 キャリア自律の促進: 対話を通じて自身のキャリアについて考える機会が増え、主体的な成長に繋がります。パーソル研究所の調査では、キャリア対話の実施後に個人のパフォーマンスが向上した人が9.5%増加、また人生満足度が向上した人が4-5%程度増加した、という結果も出ています。...